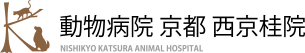ブログ
【京都市西京区】犬猫のレントゲン検査|被ばくを心配して手遅れになる前に読んでください
2025.11.21
目次
この記事を監修した獣医師
黒島稔也(どうぶつ病院京都桂 院長・JAHA獣医内科認定医)
獣医内科認定医の知識と臨床経験をもとに、飼い主様の不安に正確な情報でお応えします。

「被ばくが心配」でレントゲン検査を避けると、命に関わる病気を見逃す危険性があります。被ばく量の真実と、今すぐ病院へ行くべき症状を解説。
「被ばくが心配」が、命取りになる
「レントゲン検査をしましょう」
動物病院でこう言われたとき、あなたは何を考えますか?
「放射線の被ばくが心配…」
「何度も撮影して大丈夫なの?」
「もう少し様子を見てからでもいいんじゃ…」
その判断を、今すぐ考え直してください。
犬猫は言葉で症状を訴えることができません。飼い主様が「少し様子を見よう」と判断した数日の間に、病状が急速に悪化するケースは少なくありません。
一方、レントゲン検査の被ばく量は、健康に影響を与えるレベルの数千分の1以下です。
つまり、被ばくを心配して検査を避けることは、微小なリスクを避けるために、はるかに大きな命のリスクを取ることを意味します。
この記事では、獣医内科認定医として、以下を明確にお伝えします:
✓ 被ばく量の真実(国際基準と比較した具体的数値)
✓ 「今すぐ病院へ」行かないと起こること
✓ レントゲンで発見できる命に関わる病気
✓ 検査を受けるべき緊急症状14項目
レントゲン検査の被ばく量|国際基準で見る安全性
健康影響が出る線量との比較
国際放射線防護委員会(ICRP)の基準によれば:
健康影響が観察される線量:100mSv以上
一方、犬猫のレントゲン1回の被ばく量は:約0.01mSv
つまり、健康影響が出る線量の10,000分の1です。
日常生活との比較(具体的数値)
| 被ばく源 | 被ばく量 | レントゲン何回分? |
| 自然放射線(年間) | 2.4mSv | 240回分 |
| 東京-NY間の飛行機 | 0.1mSv | 10回分 |
| 胸部X線(人間) | 0.06mSv | 6回分 |
| 犬猫のレントゲン1回 | 0.01mSv | 1回 |
日本獣医画像診断学会によれば、動物用X線装置は国際的な安全基準に準拠して設計されており、適切な使用下では極めて安全とされています。
「何回まで撮影できますか?」への回答
米国獣医放射線学会(ACVR)によれば、診断に必要な範囲での複数回撮影は安全性が確認されています。
医学的に厳密な回数制限はなく、以下のような場合に複数回撮影を行います:
- 骨折の経過観察(治癒過程の確認)
- 心臓病のモニタリング(心拡大の進行確認)
- 誤飲物の位置確認(移動の有無)
- 治療効果の判定(改善度の評価)
角度を変えて2〜3枚撮影することは標準的な検査方法です。
レントゲン検査の被ばくリスクは、「検査をしないことで病気を見逃すリスク」と比較して、極めて小さいのです。
レントゲンで発見できる命に関わる病気
【胸部】早期発見が生死を分ける疾患
心臓病
米国獣医内科学会(ACVIM)のガイドラインでは、犬猫の心疾患において、レントゲン検査による心拡大の評価が重要とされています。治療開始が早いほど予後が良好です。
肺水腫・胸水
呼吸困難の原因を特定し、緊急処置の判断に不可欠な情報です。
肺炎・気管支炎
細菌性肺炎は、抗生物質による早期治療が重要です。
腫瘍
肺腫瘍の早期発見により、治療選択肢が広がります。
【腹部】見逃すと命に関わる異常
異物誤飲
誤飲物による腸閉塞は、発見が遅れると腸管壊死を引き起こし、生命予後が著しく悪化します。
尿路結石
完全閉塞に至る前の発見が、腎不全の予防につながります。
腸閉塞
完全閉塞では緊急手術が必要です。早期発見が救命率を上げます。
重度便秘
巨大結腸症に進行すると、生活の質が著しく低下します。
【骨格】適切な治療のために
骨折
骨折の種類・位置により治療法が異なります。適切な診断が回復を左右します。
関節疾患
変形性関節症の早期発見により、疼痛管理と生活の質の維持が可能です。
歯周病
重度歯周病は全身性の炎症を引き起こし、心臓や腎臓にも影響します。
(当院では、歯科用レントゲンを常備していないため、頭部全体的な探索となります)
レントゲン検査の仕組みと利点
X線で体の中を「見る」技術
レントゲン検査では、X線という特殊な光を体に当て、通り抜ける光と吸収される光の違いを画像化します。
**白く写る:**骨や歯(密度が高い)
**黒く写る:**肺や空気(密度が低い)
**グレーに写る:**心臓や肝臓(中間の密度)
このコントラストから、臓器の位置、形、大きさ、異常の有無を判断します。
レントゲン検査の4つの利点
1. 非侵襲的
体を傷つけずに内部を観察できます。
2. 迅速
撮影後すぐに結果を確認でき、緊急時の診断に有用です。
3. 広範囲
一度の撮影で複数の臓器を評価できます。
4. 経時的比較
過去の画像と比較して、変化を追跡できます。
**これが、健康な若齢期からレントゲンを撮影しておくことが推奨される理由です。**異常が出たときに、「正常時と比べてどう変化したか」を評価できるからです。
「麻酔は必要?」鎮静剤についての正確な情報
基本的に麻酔なしで検査可能
当院ではほとんどのケースで麻酔なしでレントゲン検査を行っています。
短時間(1回10秒程度)の撮影のため、多くの犬猫は落ち着いて受けてくれます。
鎮静剤を使用するケース
以下の場合、飼い主様の同意を得て鎮静剤を使用することがあります:
1. 極度の恐怖や攻撃性
安全に検査を実施できない場合
2. 強い痛み
骨折など、体勢を変えることで痛みが増す場合
3. 詳細な撮影
精密な画像が必要で、完全な静止が求められる場合
鎮静と麻酔の違い
- 鎮静:意識が薄れ、周りへの反応が鈍くなる状態
- 麻酔:意識が完全にない状態
レントゲン検査で使用するのは主に鎮静剤であり、麻酔よりもリスクが低い方法です。
必ず飼い主様の同意を得てから使用しますので、ご安心ください。
他の画像検査との使い分け
超音波検査(エコー)
特徴:
放射線を使わず、リアルタイムで臓器の動きを観察
得意分野:
肝臓、腎臓、膀胱など腹腔内臓器、心臓の詳細観察
軟部組織の評価に優れ、繰り返し検査が可能です。
CT検査
特徴:
体を輪切りにした画像で三次元的に評価
得意分野:
全身臓器の精査
レントゲンより被ばく量は多いですが、詳細な情報が得られます。
MRI検査
特徴:
磁石と電波を使用、放射線被ばくなし
得意分野:
脳、脊髄などの神経系
検査時間30分〜1時間、全身麻酔が必要です。
適切な検査の選択
これらの検査は、それぞれに得意分野があります。症状、疑われる病気、検査の安全性を総合的に判断して選択します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 被ばくで病気になることはありませんか?
A. 診断用レントゲンの被ばく量(0.01mSv)は、健康影響が出る線量(100mSv以上)の10,000分の1です。国際放射線防護委員会(ICRP)の基準でも、この線量で健康被害が生じることはないとされています。
Q2. 妊娠中でもレントゲンを撮れますか?
A. 妊娠中の撮影は、6週以降安全ですが、超音波検査などを併用し慎重に判断します。必ず獣医師にご相談ください。
Q3. 子犬・子猫でも安全ですか?
A. 若齢であっても、診断に必要であれば安全に撮影できます。体が小さい分、必要な放射線量はさらに少なくなります。
Q4. 年に何回まで撮影できますか?
A. 医学的に厳密な回数制限はありません。必要に応じて、年に複数回撮影しても安全です。
Q5. 撮影時、飼い主は立ち会えますか?
A. 基本的に、放射線防護の観点から飼い主様の立ち会いはご遠慮いただいています。撮影後、画像をご一緒に確認しながら説明いたします。
Q6. レントゲンとエコー、どちらが必要ですか?
A. 症状により異なります。骨や肺はレントゲン、軟部組織の詳細はエコーが得意です。両方が必要な場合もあります。
📱【迷っているなら】今すぐご相談を
「うちの子、大丈夫かな?」
「レントゲンが必要な症状なのかわからない」
その不安、そのままにしないでください。
当院へのアクセス
どうぶつ病院京都桂
〒615-8034 京都府京都市西京区下津林東芝ノ宮町2 ロアールハイツ2
駐車場:
病院前に4台駐車可能。広々とした駐車場で停めやすく、お子様連れでも安心です。
診療時間:
日曜・祝日は午後休診
LINE予約が便利です
✅ 24時間いつでも予約可能
✅ 3分で登録完了
✅ 予約の確認・変更もスマホで完結
▼今すぐLINE予約▼
https://page.line.me/602fblla?openQrModal=true
お電話でのお問い合わせも承っております。
まとめ|被ばくのリスクより、見逃すリスクを考えて
この記事の重要ポイント
✓ レントゲンの被ばく量は健康影響が出る線量の10,000分の1
✓ 緊急症状を放置すると、数時間〜数日で命に関わる
✓ レントゲン検査で早期発見できる病気は多い
✓ 「様子を見よう」が取り返しのつかない結果につながる
最後に、獣医師として伝えたいこと
臨床経験の中で、「もっと早く来ていれば」と思ったケースは数え切れません。
飼い主様が「少し様子を見よう」と判断した数日が、治療の成否を分けることがあります。
一方で、「被ばくが心配で…」という理由でレントゲン検査を避けることで健康被害が生じたケースを、私は経験したことがありません。
レントゲン検査の被ばくは、日常生活で自然に受ける放射線と変わらないレベルです。
微小なリスクを避けるために、大切などうぶつの命を危険にさらさないでください。
少しでも不安を感じたら、遠慮なくご相談ください。私たちは、飼い主様とどうぶつたちの健康を守るために、ここにいます。
どうぶつ病院京都桂
監修:黒島稔也(院長・内科認定医)
▼24時間LINE予約受付中▼
https://page.line.me/602fblla?openQrModal=true
 健康診断
健康診断