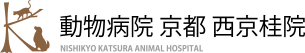ブログ
吐血の原因と病院受診の重要性について獣医師が解説
2025.10.30
目次
【最重要】血を吐いたら、理由を問わずすぐに病院へ
愛犬が血を吐いたら、緊急度の判断はせず、すぐに動物病院を受診してください。
「ほんの少しだけ」「元気そうだから」「歯磨きの後だから大丈夫かも」—そんな自己判断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
なぜ自己判断が危険なのか
- 見た目は元気でも、体内で深刻な問題が起きている可能性
- どうぶつは痛みや不調を隠す習性がある
- 「少量だから大丈夫」が、実は大量出血のサインということも
- 時間が経つほど、治療の選択肢が減っていく
「もっと早く来ていれば」と悔やまれるケースを何度も見てきました。
「何もなかった」で安心してください
「病院に行ったけど、何もなかった」—それが一番良い結果です。飼主様が「心配しすぎだった」と笑顔で帰られることほど、嬉しいことはありません。
迷う時間があるなら、すぐにご連絡ください。
京都市西京区の当院では
どうぶつ病院京都 桂
- 診療時間:9:30〜20:00(日曜・祝日は午後休診)
- LINE予約が便利です LINE予約はこちら
- 診療時間内であれば緊急対応可能
夜間の場合は、お近くの夜間救急動物病院を受診してください。
吐血の特徴
- 色:赤色〜黒っぽい色(コーヒーのかすのような色)
出血してからの時間が短ければ赤色、時間がたてば黒っぽくなります。
- 出血場所:消化器(食道、胃、腸)
犬の吐血の主な原因
犬の吐血には様々な原因があり、緊急度の高い病気から比較的軽度なものまで幅広く存在します。獣医師として18年の臨床経験から、代表的な原因を解説します。
消化器系疾患
消化管からの出血が原因で吐血します。出血の原因は以下のようなものがあります。
胃潰瘍 胃潰瘍は潰瘍の部分から出血するので、吐血や真っ黒な下痢がみられます。食欲が落ちたり、お腹を痛がるポーズをとったりなどの症状も伴う場合があります。ストレスや痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬)、ステロイド剤の長期使用が原因になることがあります。
出血性下痢症候群
急性の腸炎で、嘔吐や、いちごジャムのような血便が見られます。元気だった犬が数時間から半日ほどで急激に症状が悪化するため、注意が必要です。
消化管腫瘍 中高齢犬で注意すべき原因の1つです。腫瘍組織は脆く、わずかな刺激でも出血しやすい特徴があります。少しずつ出血が続くこともあれば、突然大量に出血することもあります。
全身性疾患による影響
凝固異常 血液中の凝固因子や血小板の異常により、止血機能が低下した状態です。肝疾患、免疫介在性疾患、薬物の副作用などが原因となります。吐血以外にも、皮膚に紫の斑点(紫斑)が出たり、歯ぐきから血が出やすくなったりします。血便や黒色便も見られる
外的要因
異物による物理的損傷 骨の破片、鋭利なおもちゃ、串などが消化管を傷つけることで出血を引き起こします。「ちょっと目を離した隙に…」ということも多いので、日頃から誤飲防止に気をつけましょう。
中毒物質の摂取 薬物などの中毒により、消化管粘膜が障害を受ける場合があります。「少しだけなら大丈夫」と思わず、どうぶつにとって危険なものは徹底的に遠ざけることが大切です。
玉ねぎやチョコでは粘膜障害がメインではない
病院へ向かう前にできること
**このセクションは「病院に行かずに様子を見る」ためのものではありません。**吐血を発見したら必ず動物病院を受診することが前提です。ここでは、病院へ搬送するまでの短時間にできることを説明します。
1. 写真を撮影する(可能であれば)
診断の参考になるため、吐血物の写真を撮影できると理想的です。ただし、撮影にこだわって受診が遅れないようにしてください。
撮影のポイント
- 色(黒っぽい、赤い、ピンク色など)
- 量(おおよその大きさが分かるように)
撮影できなくても、色や状態を言葉で説明していただければ大丈夫です。
2. 情報をメモする
病院での診断をスムーズにするため、以下の情報をメモしておきます。
記録しておきたい情報
- □ 吐血した時刻
- □ 吐血の回数
- □ おおよその量
- □ 最近食べたもの(24時間以内)
- □ 飲んでいる薬やサプリメント
- □ 普段と違う様子(食欲、元気、排便の状態など)
- □ 最近変わったこと(新しいおやつ、環境の変化など)
メモする時間がなければ、口頭で獣医師に伝えていただければ大丈夫です。
吐血を発見したら、すぐに病院へ
どうぶつが血を吐いた場合、**自己判断での応急処置のみで済ませるのは危険です。**必ず動物病院を受診してください。
なぜ自己判断が危険なのか
吐血の原因は多岐にわたり、見た目だけでは重症度を判断できません。「少量だから大丈夫」「元気そうだから様子を見よう」という判断が、取り返しのつかない事態につながることがあります。
- 見た目は少量でも、体内で大量出血している可能性
- 元気に見えても、急激に悪化する病気の可能性
- 素人判断での長時間の絶食・絶水が脱水や低血糖を招く危険
**獣医師としての経験から、吐血を「様子見」して手遅れになったケースを何度も見てきました。
予防のために今日からできること
吐血のリスクを減らすため、日常的にできることをご紹介します。ただし、予防していても吐血が起きた場合は、必ず動物病院を受診してください。
誤飲防止の工夫
異物による消化管損傷を防ぐため、生活環境を見直しましょう。
- ゴミ箱はフタ付きにする
- 危険なものは高い場所に置く
- 散歩は短いリードで拾い食いを防ぐ
- 鶏の骨、竹串などは確実に処分する
中毒物質を遠ざける
絶対に与えてはいけないもの
- 玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニク
- チョコレート
- ぶどう、レーズン
- キシリトール入りの食品
年1-2回の健康診断
病気の早期発見が重症化を防ぎます。
推奨頻度
- 7歳未満:年1回
- 7歳以上:年2回
- 10歳以上:年2回+気になる症状があればすぐ受診
定期健診で「問題なし」と言われていても、吐血などの異常が見られたら、次の健診を待たずにすぐに受診してください。
まとめ
どうぶつが血を吐いた時は、**「様子を見る」という選択肢はありません。**必ず動物病院を受診してください。
吐血で最も重要なこと
- 緊急度を確認(ぐったりしている、呼吸が苦しそうなら夜間でも受診)
- 色や量を記録(写真撮影が理想)
- 自己判断せず、すぐに病院へ
「少量だから大丈夫」「元気そうだから様子を見よう」という判断が、命に関わる事態を招くことがあります。
獣医師からのお願い
獣医師として18年、多くのどうぶつを診てきましたが、「もっと早く連れてきていれば」と悔やまれるケースが少なくありません。
迷ったら、すぐにご連絡ください。
飼主様の「何か変だな」という直感は、多くの場合正しいものです。その直感を信じて、早めの受診をお願いします。
当院での対応
どうぶつ病院京都 桂では、吐血などの消化器症状に対して、内科認定医による専門的な診療を行っています。
当院の特徴
- 獣医内科認定医(JAHA認定)による診療
- 獣医師歴18年、認定医歴12年の経験
- 京都市内だけでなく、他府県からも来院いただいています
アクセス・診療時間
- 住所:京都市西京区下津林東芝ノ宮町2 ロアールハイツ2
- 電話:075-382-0091
- 診療時間:9:30〜20:00(日曜・祝日は午後休診)
ご予約方法
LINE予約が便利です LINE予約はこちら
「これって大丈夫かな?」と少しでも不安に思ったら、お気軽にお問い合わせください。飼主様の不安な気持ちを大切に、丁寧に診察いたします。
監修:黒島稔也(どうぶつ病院京都 桂 院長・JAHA獣医内科認定医) 獣医師歴18年、認定医歴12年
 健康診断
健康診断